SNSで見るフルレバ挑戦と無計画な信用取引の危険性
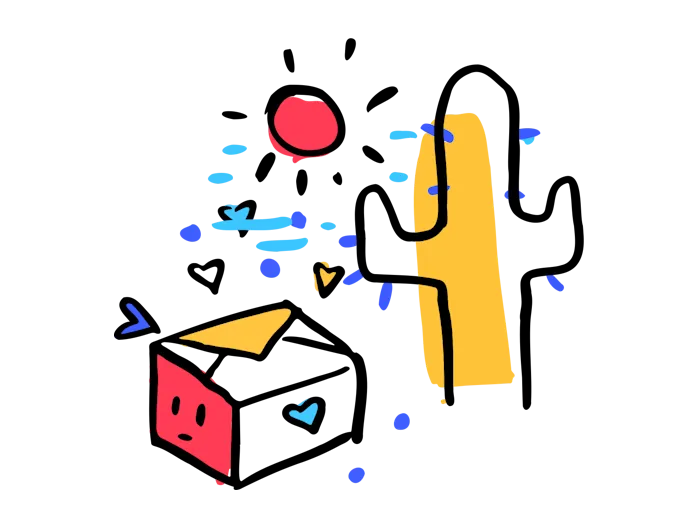
SNSなどで
「チャンス!いけると思ったら信用フルレバで入ります!」
といった投稿を見かけると思います。
SNSで熱い投資の投稿を見ると、つい自分もやってみたくなりますよね。
もちろん結果は分かりませんが、筆者としては、
「あ〜、ちょっと危なそうだな……」
と思いつつも、他人のスタイルや資金管理に口を出すべきことではないので静観しています。
実際その日はそのまま勝って派手な収益報告を上げている投稿も多数あります。
しかし日を追って数日後、急に投稿がぱったり途絶えることもよくあります。
実際の真意は分かりませんが、
「あぁ、もしかしたら厳しい結果になったのかな……」
と感じることも。
💡 かの有名なBNF氏は総資産近くでフルレバだったという話も聞いた事があります。
投資手法に正解はないと思ってるので筆者の感想・意見を含みます。
こうした光景が、「 信用取引 =危険」というイメージを強める一因となっていると思います。
ポイント
- 無計画な 信用取引 は危険です
- 資金をフルで使うと、少しの下落でも 追証 や 強制決済 のリスク
✅️ 本記事は 信用取引 を推奨するものではありません。
あくまで投資判断はご自身の判断で行ってください。
現物フルポジションのリスクとは?
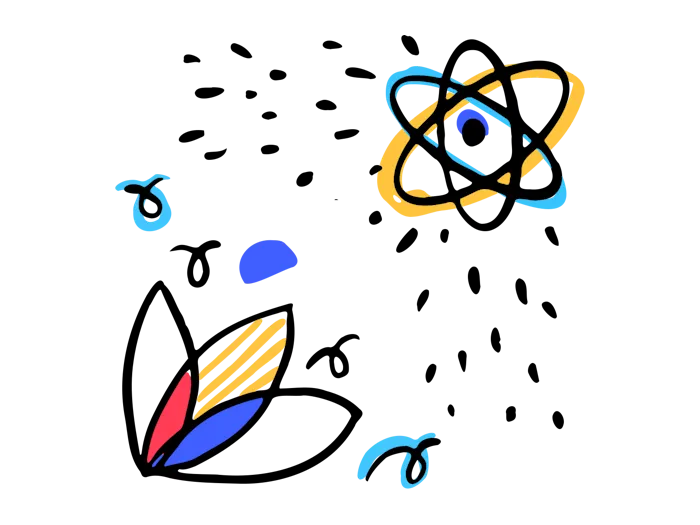
「現物=安全」と考える投資家も多いですが、現物フル ポジション にも注意すべきリスクがあります
例:資金100万円を1銘柄に投資した場合
- 下落10% → 10万円の損失
- ナンピンや 損切り の柔軟性が低下
- 精神的負荷が大きく冷静な判断が難しくなる
銘柄 | 損益 |
A | -10% → -10万円 |
💡 ナンピン(いい意味での買い増し)
ナンピンというと悪いイメージで語られがちですが、ここで言うのは計画的な買い増しや分割発注のことです。
あらかじめ資金や回数を決めておくことで、損失コントロールがしやすく、精神的にも余裕を持って取引できます。
信用取引で分散すると効率的にリスクを“分割”できる
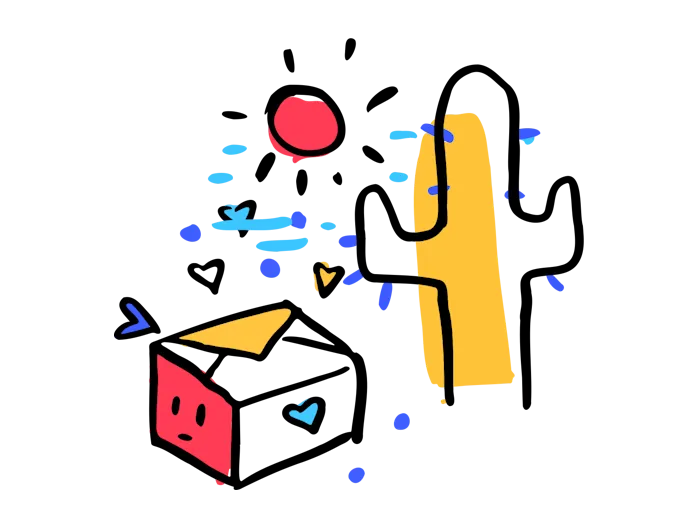
信用取引 は レバレッジ で危険に見えますが、使い方次第で安全です。
リスクを分散するための「資金管理ツール」
レバレッジ は単に ロット を増やすためではなく、リスクを分散するための「資金管理ツール」として利用するのがおすすめです。適切に分散することで、リターンも効率的に回収可能です。
例:資金100万円を3銘柄に分散
銘柄Aが-10%,Bが±0%,Cが+10%という変動だったとします。
単純な例ですが、日常的に起こりうる事はイメージ出来ると思います。
銘柄 | 損益 |
A | -10% → -3.3万円 |
B | ±0% → 0円 |
C | +10% → +3.3万円 |
合計損益 = 0円
現物フルだと-10万円ですが、分散することで損益の波を打ち消せます。
さらに 信用取引 で分散すると同じ100万円でも余力を残しているため、柔軟性もあり精神的・資金的な負荷が軽減されます。
⚠️ 注意:
信用取引 にはその他金利や手数料がかかります。市場全体が大きく下がると分散の効果が薄れる場合もあるのでしっかりした資金管理と設計が必須です。(例で出した3銘柄全部が大きく下げる事もありえる)
安全に分散するための3つの目安
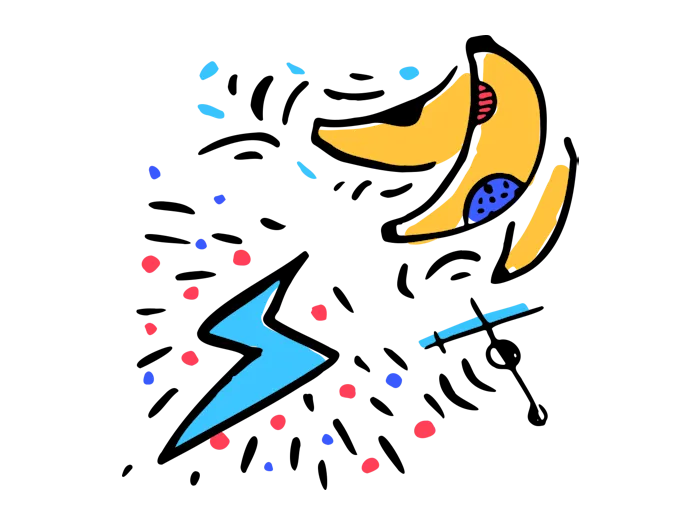
1. 余力30%以上を目安に確保
急落でも 強制決済 リスクを低減
軽い根拠・参考事例:
過去10年の日経平均の1日最大下落幅は平均5〜10%程度(例: 2020年コロナショックで約10%下落)。3銘柄分散で1銘柄が10%下がっても、余力30%あれば 追証 を回避しやすく、資金を守れる可能性が高い。ただし、リーマンショックのような極端な暴落時には、この余力だけでは保てない場合があります。
2. 同業種・同テーマに偏らない
ニュースや業界ショックによって同じセクションやテーマは似たような動きをする事が多いです。
計画的にわける事で同時下落を避けられます。
軽い根拠・参考事例:
2020年の新型コロナウイルス流行による航空・旅行業界の暴落や、2022年のテクノロジー株の下落(例:メタやテスラなど)では、同じテーマに集中していた投資家が大きな損失を被った事例があります。一方、エネルギーやヘルスケアなど異なるセクターに分散していた場合は、下落の影響を抑えられたケースも見られました。
3. ボラティリティで建玉調整
値動き大きい銘柄は小さく、安定銘柄はやや大きく
軽い根拠・参考事例:
2022年のゲーム業界不振(ソシャゲ売上減速)で、ソーシャルゲーム大手サイバーエージェント(4751)は数ヶ月で株価が約40%急落し、大きな ポジション を取った投資家は急激な含み損に直面しました。一方、日経225の大型株(例:トヨタや三菱UFJフィナンシャル・グループ)は同期間で1〜3%程度の変動が多く、大きめの 建玉 でもリスクが比較的抑えられた事例があります。
いずれも時間軸や銘柄・ 損切り の設計次第なので目安です。
実際には、 バックテスト などを利用して余力を設定するのがおすすめです。
👉️ バックテスト についてはこちらで詳しく紹介しています。
バックテストで戦略設計と退場リスクを確認する
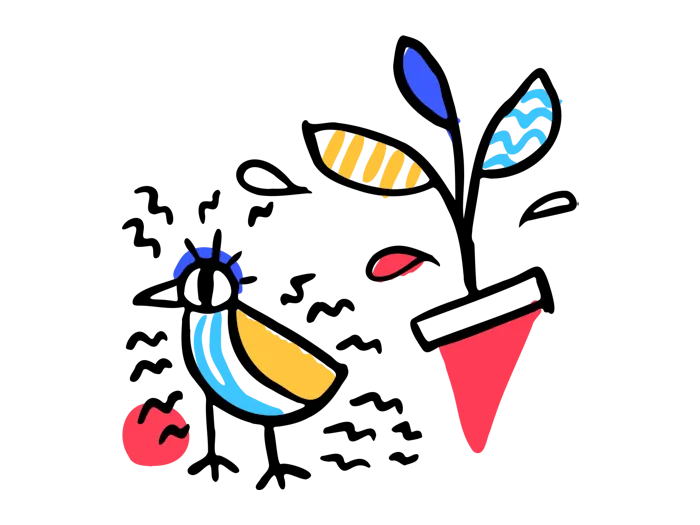
- 無計画な信用は危険 → 設計次第で安全
- 現物フルも余力ゼロでリスク大
- 信用分散は 資金効率 +リスク分散が両立
- 業種・ボラ・余力で調整し、分散の質を高める
また、今回は極端な例で紹介しましたが、現物でももちろん分散は可能です。
つまりは、現物・信用の区分ではなく、設計が大事。
信用取引
は
追証
や保有資金以上の損失が出る可能性がありますが、
適切な分散・余力管理でリスクをコントロールできます。
💡 信用取引 =危険、現物=安全という単純な考えではなく
リスクは“資金と戦略設計”で決まることを理解し、安全に信用を活用するのがおすすめです。
戦略設計はバックテストで過去データで検証・運用がおすすめ。
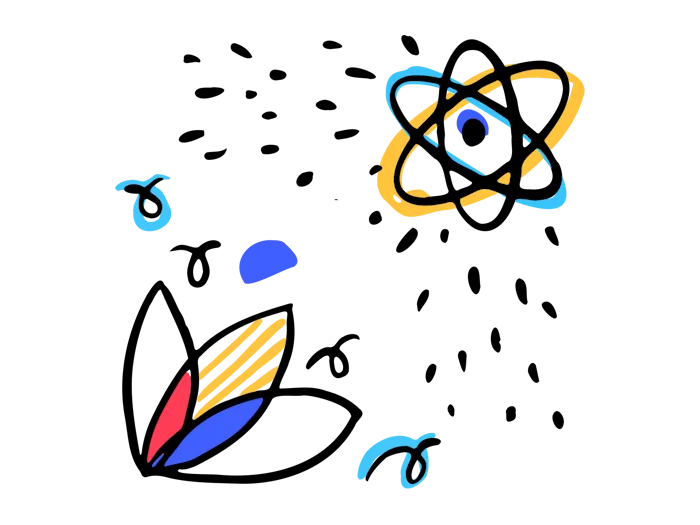
バックテスト を利用すれば例に出した事例や
「特定の日にある銘柄に200%資金を入れたいた場合にどれだけ損失がでたか。」
といった事例をデータに基づいて確認する事ができます。
バルサラの破産確率と分散を組み合わせる
さらに発展した設計として、
勝率
やペイオフレシオといった指標と利用した
バルサラ
の
破産確率
と分散を組み合わせると、理論上の退場リスクを限りなくゼロに近づけられる設計も可能です。
💡 注: バルサラ の 破産確率 とは、 勝率 や 損益比率 から資金がゼロになる確率を計算する数理モデルで、 リスク管理 に役立ちます。
戦略設計に関しては下記でも詳しく紹介しています。

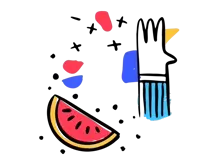
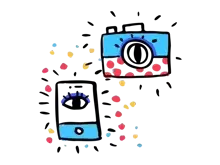

 で学ぶ
で学ぶ

